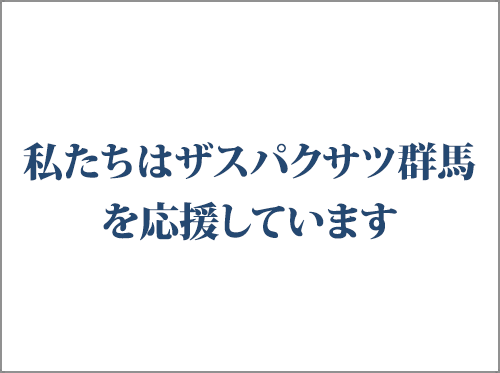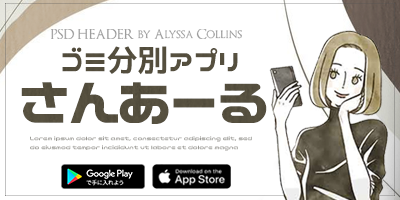お引っ越しを予定している方の中には、
「ご近所さんへの挨拶ってどうすれば良いのだろう?」
という疑問を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、引っ越しのご挨拶は必須なのか、挨拶をする際のマナーはあるのかということについて、詳しく解説していきます。
引っ越しの挨拶って必要?
結論から言ってしまうと、引っ越しの挨拶は義務ではありません。
女性の一人暮らしの場合は、
「私は一人暮らしをしていますよ」
と、近隣に知らせてしまうことになりますので、防犯上の理由からあえて挨拶をしないという選択をする方もいます。
ただ、基本的には引っ越し後は、近隣に挨拶をした方が良いと言えます。
特に地方に引っ越しをする場合、近隣との繋がりや関係性が深くなることもありますので、良いお付き合いをしていくためにも、相手に不安や心配をかけないためにも、挨拶をしておくと良いでしょう。
引っ越しの挨拶をするメリットとは?
では次に、引っ越しの挨拶をするメリットについて、詳しく解説していきます。
・・困った時に相談ができる
引っ越しの挨拶をしておけば、困った時に相談しやすくなります。
引っ越し直後というのは、ゴミの出し方や地域の集まりなど、わからないことがたくさん出てきますよね。
引っ越しの挨拶をして、近所の方と顔見知りになっておけば、気軽に質問や相談ができるようになりますので、快適に生活しやすくなるのです。
・・子育ての理解を得られる
引っ越しの挨拶をしておくことで、騒音問題などにもある程度目を瞑ってもらえる可能性が高くなります。
また、近所の方と顔みしりになっておけば、子どもを見守ってくれたり、適度に声がけをしてくれたりしますので、「子どもを守る」という意味でも効果的です。
引っ越しの挨拶ってそもそも誰にすればいいの?
では次に、引っ越しの挨拶は誰にすればいいのか、ということについて詳しく解説していきます。
・・アパートやマンションに引っ越した場合
アパートやマンションなどの集合住宅に引っ越しをした場合、上下左右の住人に挨拶をするようにしましょう。
上の階の住人に挨拶をしておくことで、騒音などに対する配慮をしてもらいやすくなりますし、下の階の住人に挨拶をしておくことで、多少の騒音にも目を瞑ってもらいやすくなります。
両隣の方に挨拶をしておくことで、お互いに安心感を得られます。
2軒先の部屋については、隣接しているわけではありませんので、挨拶をしなくても問題ありません。
・・一軒家に引っ越した場合
一軒家に引っ越しをした場合は、集合住宅に比べると挨拶の範囲が広くなります。
具体的には、自宅を取り囲んでいる家全てに挨拶をするようにしましょう。
地方の一軒家に引っ越しをした場合、ご近所づきあいが盛んに行われていることも多く、挨拶をした家としない家が出てきてしまうと、
「あの家には挨拶をしたのに、うちにはこなかった」
というようなトラブルを招きやすくなります。
範囲が広くなる分手間もかかりますが、挨拶をしておくことで、気持ちよく生活しやすくなりますので、できるだけ早い段階で済ませておくようにしましょう。
引っ越しの挨拶はどのタイミングですべき?
引っ越しの挨拶のタイミングで悩んでしまう方も多いです。
あまりにも非常識な時間を選んでしまうと、逆効果になってしまうこともあります。
これから引越しをする方、引っ越しの挨拶をする予定の方は、以下の時間帯を参考にしながら挨拶のタイミングを見計らっていきましょう。
・・引っ越し前日、もしくは当日の明るい時間帯がベスト
引っ越しの挨拶は、引っ越し前日、もしくは当日の明るい時間帯に行うのがベストです。
引っ越し前日に挨拶をしておくことで、当日の騒音などにも目を瞑ってもらいやすくなります。
ただ、場合によっては前日に挨拶ができないケースや、積み下ろしに追われて挨拶ができないケースもあるでしょう。
そんな時は、積み下ろしがひと段落したタイミングで挨拶をすれば問題ありません。
明るい時間帯と言っても、お昼時や夜は避けた方が良いでしょう。
具体的には、
・12時~13時以外
・19時以降
の時間帯を選んだ方が、相手に迷惑がかかりません。
明るい時間帯に挨拶ができなかった場合、20時くらいまでであれば常識の範囲内と考えられますが、不快に感じる方もいますので、18時を過ぎた場合は翌日に回した方が良いでしょう。
・・留守だった場合は挨拶状でも良い
「何回か訪問したが、相手が留守だった」
というような場合、無理に訪問する必要はありません。
生活リズムは人それぞれ異なりますので、昼間の時間帯に寝ている方もいます。
無理に訪問してしまうと、かえって相手を不快にさせてしまいますので、その場合は挨拶状と手土産を玄関先に置いておきましょう。
引っ越しの挨拶をする前に知っておくべきマナー6選
引っ越しの挨拶をするときは、相手に好印象を持ってもらうことが大切です。
最低限のマナーがなっていないと、
「厄介な人が引っ越してきたな」
「できるだけ関わりたくないな」
と思われてしまうこともあり、挨拶の意味がなくなってしまいます。
以下、引っ越しの挨拶をする前に覚えておくべき最低限のマナーについて、詳しく解説していきます。
・・身だしなみを整える
引っ越しの挨拶をする際は、身だしなみを整えましょう。
スーツなど、堅苦しい服装を選ぶ必要はありませんが、清潔感のある服装を意識することが大切です。
ジャージやパジャマなど、不快感を与える可能性のある服装は避けるようにしてください。
また、寝ぐせがついていたり、髭が伸びていたりすると、相手にマイナスのイメージを持たれやすくなりますので注意が必要です。
・・とにかく笑顔で接する
挨拶をする際は、とにかく笑顔で接するようにしましょう。
第一印象は非常に重要となり、この段階で相手からネガティブなイメージを持たれると、その印象を覆すのはかなり難しくなります。
無表情で挨拶をしたり、不愛想だったりすると、相手から警戒される可能性が高くなりますので注意しましょう。
・・丁寧な言葉遣いを意識する
相手に好印象を与えるためには、丁寧な言葉遣いを意識することが大切です。
・砕けた敬語
・ため口
などは、相手に不快感を与える原因になりますので、正しい日本語を使って挨拶をするようにしましょう。
・・挨拶をする時間に注意
先ほども解説したように、引っ越しの挨拶は前日あるいは当日までに済ませておくことが大切です。
ただ、朝早くに行ったり、夜遅くに行ったりすると、
「非常識だな」
と思われる可能性が高くなります。
相手から好感を持ってもらうためにも、19時を過ぎてしまった場合は、次の日の日中に訪問するようにしましょう。
・・手土産を持って行く
引っ越しの挨拶をする際は、手土産を持っていくと良いでしょう。
「絶対に手土産を持っていかなければならない」
というわけではありませんが、手ぶらよりはちょっとした手土産を持って行った方が好印象を与えやすいです。
ただ、あまりにも高価な手土産を選んでしまうと、相手に気を遣わせてしまいますので、500円から1,000円前後のものを選ぶようにしてください。
・・挨拶はできるだけ手短に
引っ越しの挨拶は、できるだけ手短に済ませましょう。
中には、ダラダラと長話をしてしまったり、無理に会話を繋げようとしてしまったりする方もいますが、その瞬間も相手の時間を奪っていることになりますので、最低限の挨拶をしてできるだけ早く引き上げましょう。
引っ越しの挨拶で持っていく手土産は何がいい?
最後に、引っ越しの挨拶におすすめの手土産をいくつか紹介していきます。
・・タオルや手ぬぐい
引っ越しの挨拶で持っていく手土産は、利便性の高い日用品がおすすめです。
タオルや手ぬぐいであれば、様々な場面で使用することができますので、喜んでもらえる可能性が高くなります。
タオルや手ぬぐいをそのまま渡してしまうと、雑な印象を与えてしまいますので、簡単でも構いませんのでラッピングをしておくことをおすすめします。
・・お菓子
クッキーやおせんべいなどのお菓子を手土産にするのもおすすめです。
ただ、人によって好みが別れますので、無難なものを選ぶようにしてください。
あまりにも賞味期限が短いものは、かえって煙たがられることもありますので、最低でも1か月は日持ちするものを選んだ方が良いでしょう。
・・金券
商品券やクオカード、図書カードなども喜ばれやすいと言えます。
これらの金券は、年齢や性別問わず利用できるものですので、相手の家族構成がわからない場合にもおすすめです。
また、金券はかなりコンパクトですので、持ち運びやラッピングなどもしやすいです。
・・お茶や紅茶
「相手の好みがわからない」
「手土産を選ぶのが面倒くさい」
という場合は、お茶や紅茶を選んでみると良いでしょう。
お茶や紅茶は、どちらかというと上品な手土産になりますので、相手から好印象を持ってもらいやすいと言えます。
まとめ
引っ越しの挨拶は必須ではありませんが、近隣と良好な関係を築くためにも、子どもを守るという意味でも、できるだけ早い段階で済ませた方が良いでしょう。
特に地方はご近所付き合いが盛んですので、挨拶をしておかないと、相手から警戒されてしまったり、冷たくあしらわれてしまったりすることもあります。
挨拶を行う際は、時間帯やマナーに関する知識を身に着けておくことが大切です。
非常識な時間に行ってしまったり、非常識な態度を取ってしまったりすると、マイナスのイメージを与えてしまう可能性が高くなり、良好な関係を築きにくくなってしまいます。
近隣トラブルを防ぎ、快適に生活をしていくためにも、今回紹介したことを参考にしながら挨拶を行ってみてください。
ただし、女性の一人暮らしなど、挨拶をしない方がいい場合もありますので、臨機応変に対応していくことをおすすめします。